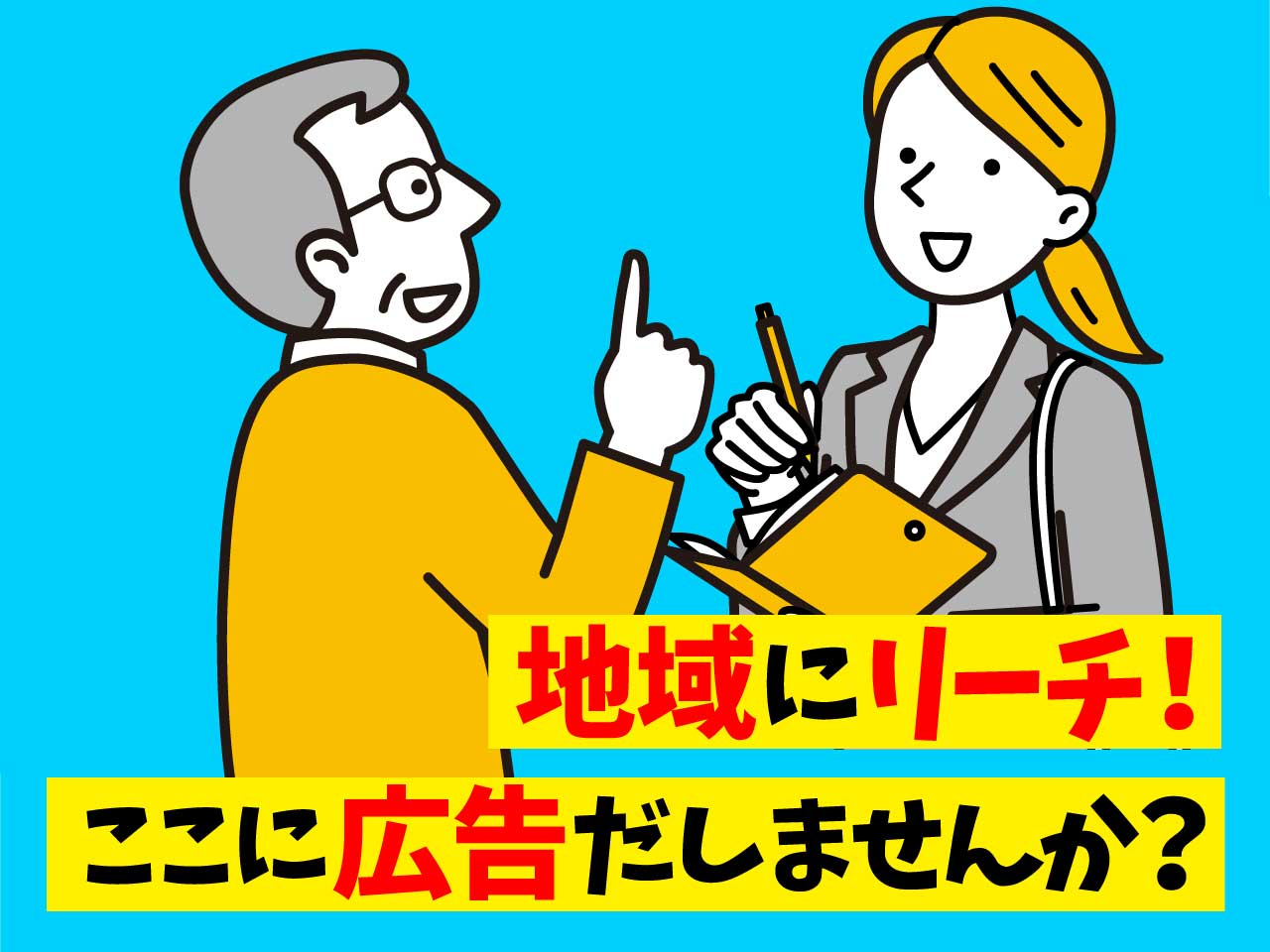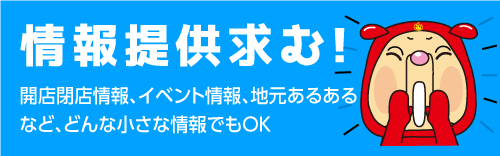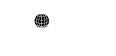【太宰府市】あなた、200年近くもここに立ってたの!? さいふ詣りの旅人が身を清めた川に立つ三浦の碑

江戸時代、全国各地の有名寺社に参詣し、道中の風光を楽しむ旅行が流行りました。「お伊勢詣り」や「こんぴら詣り」と同様に、太宰府天満宮へ参詣する「さいふ詣り」も大変な人気だったそうです。
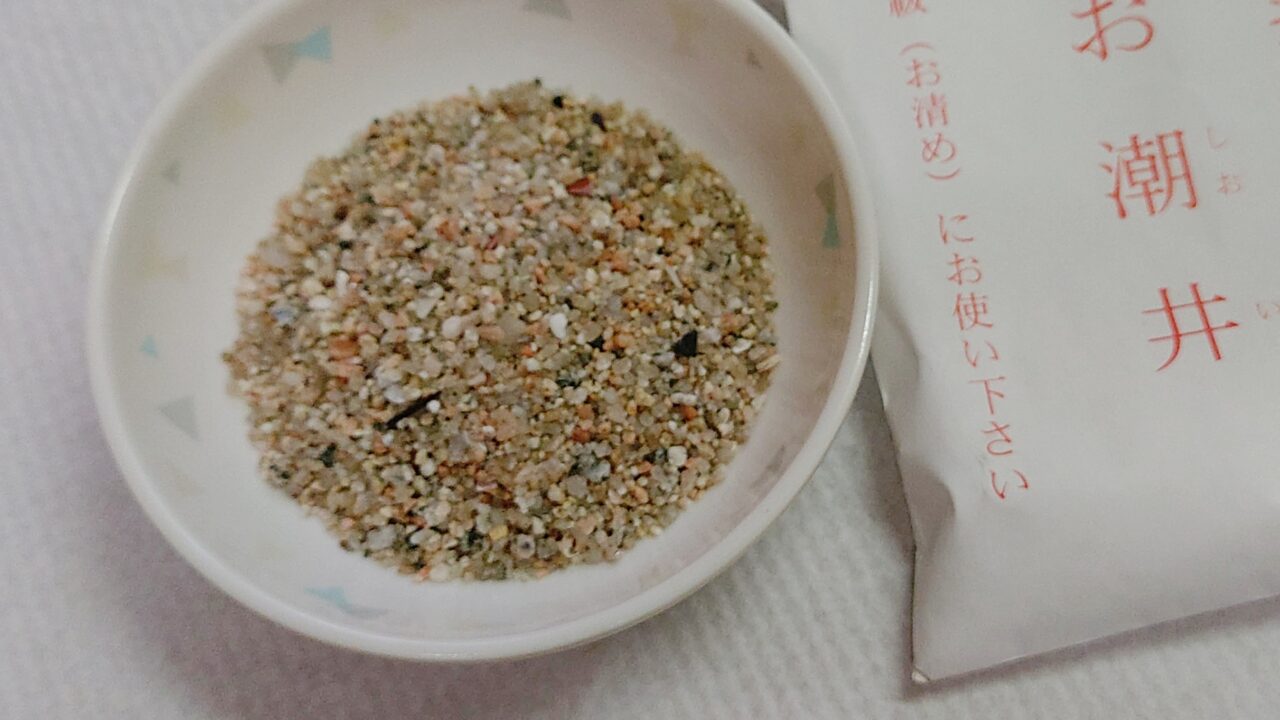
(筆者が他の神社でいただいた御塩井)
日田街道から分かれ、太宰府天満宮に向かう道の途中にあるのがこちらの五条橋です。ここに立つのが通称・三浦の碑「奉納三所塩食碑」です。伊勢・二見浦、紀州・和歌浦、博多・箱崎浦の三つの浦から御塩井を取り寄せて、川の水を清めました。

さいふ詣りの参詣者はこの川で手を洗い、口をすすぎ、体や心の汚れを祓い、宰府宿へ入ったとのことです。文政3年(1830年)、ここに建てられたのが三浦の碑。昭和48年(1973年)の水害で流失しましたが、その後、川底から発見され、現在の場所へ再設置されました。

この碑文は博多の聖福寺で名僧と呼ばれた仙厓和尚によるもの。神社にまつわる場所にお寺の僧が関わっているというのは、神仏習合のひとつなのでしょうか。日本人の宗教観を表しているようで面白い話ですね。

この通りは現在でも太宰府天満宮へ向かう車でいつも渋滞するところ。近くを通りかかったら「200年近くお疲れ様です」とぜひ声をかけてください。
奉納三所塩食碑(三浦の碑)はこちら↓